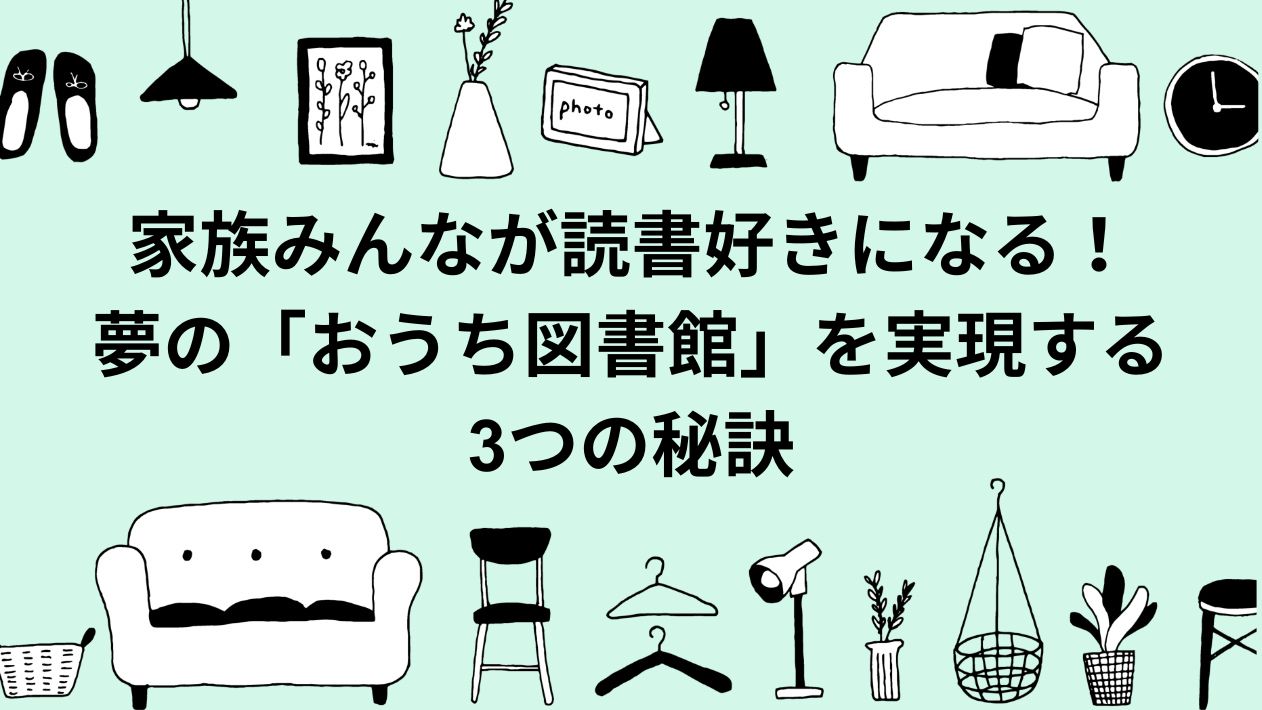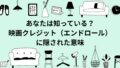「最近、子どもが本を読まなくなった」「リビングに本が散らかり放題になっている」。そんな悩みはありませんか。本を読むことは、子どもの未来にとって、そして私たち大人の心を豊かにするために、とても大切な習慣です。しかし、ただ「本を読みなさい」と言うだけでは、なかなか家族の心には響きません。もし、家族が自然と本を手に取り、読書について語り合うような空間が自宅にあったら、どうでしょうか。それが「おうち図書館」です。おうち図書館とは、単なる本の収納場所ではありません。家族みんなが「読みたい」という気持ちを育み、本を通じてつながりを深めるための「生きた空間」のことです。この記事では、お金や広いスペースがなくても実現できる、家族みんなが読書好きになる「おうち図書館」作りの3つの秘訣をご紹介します。
秘訣その1「空間」- 家族が自然と集まる「居場所」を作る
最初の秘訣は、物理的な「空間づくり」です。どれほど素晴らしい本が揃っていても、それが薄暗い廊下の隅や、物置同然の部屋に押し込められていては、誰も手に取ろうとは思いません。おうち図書館を成功させる鍵は、「アクセスしやすさ」と「居心地の良さ」です。家族が多くの時間を過ごす場所に、自然と本が存在する環境を整えることから始めましょう。大掛かりなリフォームや高価な本棚は必要ありません。今ある空間を少し見直すだけで、読書への第一歩がぐっと近くなります。
「読書スペース」はリビングの一角から
専用の書斎を作る必要はありません。おうち図書館に最適な場所は、家族が最も集まるリビングルームです。テレビのすぐそばではなく、少し落ち着けるリビングの一角に、小さな「読書スペース」を設けてみましょう。例えば、ソファの横に小さな棚を置き、読みかけの本や家族が推薦する本を数冊置くだけでも立派な読書スペースになります。大切なのは、生活動線の中に自然と本が目に入る仕組みを作ることです。子ども部屋に本を隔離するのではなく、リビングで親が読書する姿を見せることも、子どもの読書意欲を刺激する大切な要素となります。
魅力的な「本の見せ方」で興味を引く
本棚にぎっしりと背表紙だけが並んでいる状態は、図書館というよりは「倉庫」に近いかもしれません。家族の興味を引くためには、書店やカフェのような魅力的な「本の見せ方」いわゆるディスプレイを意識することが重要です。特に小さなお子さんがいるご家庭では、表紙の絵柄が見えるように本を飾る「面出し(つらだし)展示」が非常に効果的です。表紙が見えるだけで、子どもたちは「あの本が読みたい」と自ら手を伸ばすようになります。また、季節ごとにテーマを決めて(例えば、夏なら「冒険の本」や「怖い話」)、ディスプレイを変えるのも楽しい試みです。本棚の一部をお気に入りの雑貨や観葉植物と一緒に飾ることで、空間全体がより洗練され、居心地の良い雰囲気になります。
「居心地の良い」雰囲気は小物で演出
おうち図書館は「居心地の良い」場所でなければなりません。本を読むという行為は、リラックスした状態でこそ集中できるものです。その雰囲気作りは、簡単な小物が助けてくれます。例えば、読書スペースの床に肌触りの良い小さなラグを敷くだけで、そこは特別な空間になります。手元を優しく照らす読書灯(スタンドライト)を置けば、夜の読書時間が一層豊かなものになるでしょう。また、一人掛けの楽な椅子や、床に直接座るための大きなクッションを用意するのも良い方法です。
秘訣その2「仕組み」- 家族全員で運営する「我が家のルール」
夢のおうち図書館を実現するための2つ目の秘訣は、家族全員で参加する「仕組みづくり」です。立派な空間ができあがっても、そこがすぐに散らかったり、誰も使わなくなったりしては意味がありません。おうち図書館を「生きた空間」として維持し、発展させていくためには、明確でありながらも堅苦しくない「我が家のルール」が必要です。このルール作りこそが、家族のコミュニケーションを促し、図書館への愛着を生むきっかけとなります。大切なのは、親が一方的に決めるのではなく、家族みんなで話し合って決めていくプロセスそのものです。
「選書ルール」は家族会議で決める
おうち図書館に置く本は、誰が選びますか。親が「子どもに読ませたい本」だけを並べてしまうと、それは「図書館」ではなく「課題」になってしまいます。そこで重要になるのが「選書ルール」です。月に一度「家族会議」を開き、みんなで「今月、図書館に新しく迎えたい本」を話し合ってみてはいかがでしょうか。公立図書館から借りてくる本、新しく購入する本、それぞれ予算や冊数を決めて、家族それぞれの希望を出し合います。親はビジネス書、子どもは図鑑やマンガ、それで良いのです。多様なジャンルの本が集まることで、お互いの興味を知るきっかけにもなります。
「図書館習慣」を育む簡単なルール
おうち図書館をきれいに保ち、誰もが使いやすくするための「図書館習慣」も大切です。といっても、公立図書館のような厳格な貸出カードは必要ありません。例えば「本を読んだら、元の場所に戻す」という基本的なルールや、「読み終わった本を入れる専用の箱(返却ボックス)」を設けるだけでも、散らかり防止に大きな効果があります。また「借りる時は、棚に置かれた自分の名前のクリップを挟んでおく」といった簡単な仕組み(本のバトン)を取り入れるのも良いでしょう。
秘訣その3「対話」- 本が家族の「共通言語」になる
おうち図書館作りの最後の、そして最も重要な秘訣は、「対話」を生み出す仕掛けです。おうち図書館の最終的なゴールは、本をたくさん読むこと以上に、本を通じて家族の「親子の対話」を豊かにすることにあります。本は、知識や物語を私たちに与えてくれるだけでなく、人と人をつなぐ強力な媒介となります。共通の物語について語り合ったり、自分が感動した一節を教え合ったりすることで、家族の絆はより一層深まります。読書が「個人の作業」で終わらず、「家族の体験」へと昇華するような仕掛けを作っていきましょう。
「ブックレビュー」で感想を共有する
読んだ本の「感想共有」いわゆるブックレビューの時間を設けることは、非常に有効な対話の仕掛けです。しかし、感想文を書かせるような堅苦しいものである必要は全くありません。例えば、夕食の時間に「今日読んだ本で面白かったところ」を一人ずつ発表するだけでも構いません。あるいは、図書館スペースにコルクボードを設置し、読んだ本の表紙のコピーと「面白かった!」「泣けた!」など一言の感想を書いた付箋を貼る「我が家のベストセラーコーナー」を作るのも楽しい試みです。他人の感想を見て「じゃあ私も読んでみようかな」と、次の読書につながるきっかけにもなります。
「本のバトン」で感動をつなぐ
家族だからこそできる素敵な習慣が、読み終えた本を次の人へ手渡す「本のバトン」です。親が読んで感動した本を「あなたもきっと好きだと思うよ」と子どもに勧めたり、逆に子どもが夢中になった本を「お父さんも読んでみてよ」と手渡したり。本が家族の中を巡ることで、感動が連鎖していきます。無理に感想を言い合う必要はありません。ただ「あの本、面白かったね」と一言交わすだけで、同じ世界観を共有できたという喜びが生まれます。
「お気に入りの本」が親子の対話を生む
おうち図書館は、家族それぞれの「お気に入りの本」が集まる場所でもあります。親が自分の人生に影響を与えた一冊を本棚に並べ、いつか子どもがそれを手に取る日を想像するのも素敵なことです。また、子どもが大切にしている絵本を、親が改めて読み返すことで、子どもの視点や興味関心を深く理解できることもあります。「どうしてこの本が好きなの?」という素朴な疑問から始まる「親子の対話」は、お互いの価値観を知る絶好の機会となります。
まとめ
家族みんなが読書好きになる「おうち図書館」を実現するためには、3つの秘訣があります。第一に、リビングの一角など、家族が自然と集まる場所に「居心地の良い」読書スペースを作り、魅力的な「本の見せ方」を工夫すること。第二に、「家族会議」で「選書ルール」を決めるなど、家族全員で運営する「仕組み」を作り、「図書館習慣」を育むこと。そして第三に、「ブックレビュー」や「本のバトン」を通じて「親子の対話」を生み出し、本を家族の共通体験にすることです。
おうち図書館作りは、一日で完成するものではありません。家族の成長や本の増減に合わせて、レイアウトやルールを柔軟に変えていく、まさに「生きている」プロジェクトです。大切なのは、完璧な本棚を目指すことではなく、家族が本を通じて語り合い、心を通わせる時間を少しでも増やすことです。まずは今週末、「我が家のおうち図書館、どう作る?」と話し合ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。